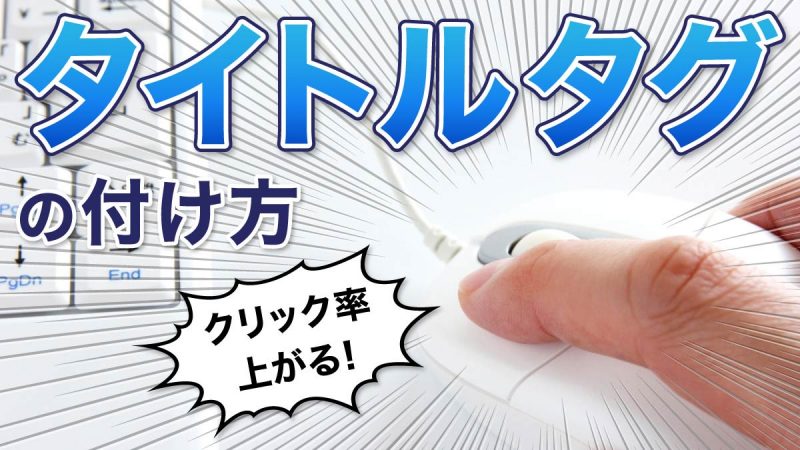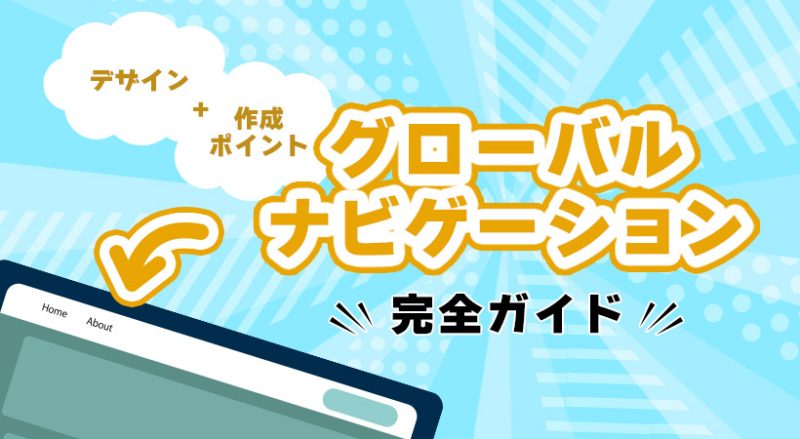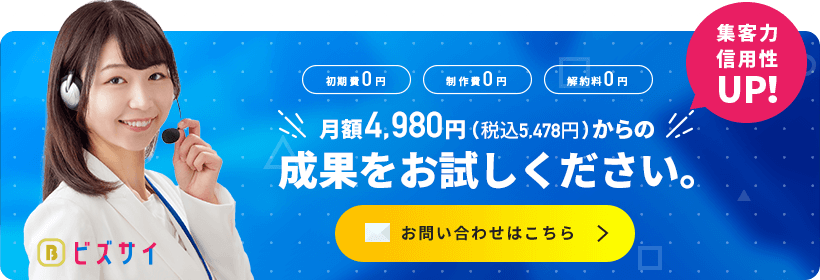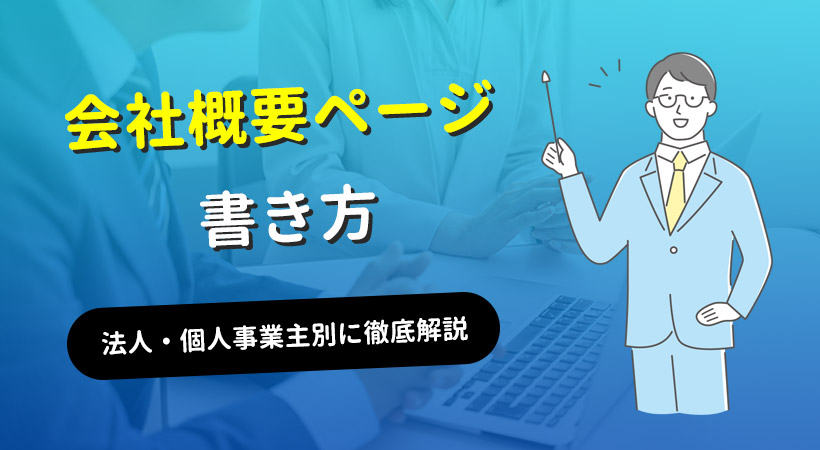ホームページの改善5ステップを徹底解説!具体的な方法11選も紹介

ホームページは公開して終わりではなく、目的・目標の達成に向けて改善し続ける必要があります。
『具体的にホームページのどこを改善すればよいかわからない』
『ホームページからの問い合わせ数を増やしたい』
上記の疑問に答え、今回の記事では、ホームページの改善ステップや原因の見つけ方、具体的な改善のアイデアなどを詳しく解説します。
本記事を読めば、ホームページのどこに原因があるかがわかり、改善案のヒントも得られます。
実際に施策を実行し、成果の出るホームページの構築を目指しましょう。
※本記事の情報は、2025年10月9日時点のものです
ホームページ改善の5ステップとポイント
ホームページの改善を進めるには、次のような手順で進めていくのがおすすめです。
- ホームページ改善の目的・目標を確認
- ホームページの現状を分析する
- ホームページの改善案を洗い出す
- 改善案に優先順位をつける
- 改善案を実施し効果検証を行う
各ステップの詳しいやり方やポイントを紹介します。
1.ホームページ改善の目的・目標を確認
なぜホームページを改善したいのか、どのような方向で改善したいのかを確認しましょう。
ホームページを改善する目的の一例を挙げると、次になります。
- ホームページへのアクセス数を増やしたい
- ホームページ経由の資料請求数を増やしたい
- ホームページ内をもっと回遊させたい
一口にホームページ改善といっても、目的はさまざまです。
目的が異なれば、分析するポイントや最適な施策も異なってくるため、方針を定めるためにも、明確化するのが重要です。
また、目的をより具体的な数字にして目標を設定します。
たとえば、先ほど挙げたホームページ改善の目的であれば、次のように目標を定めます。
- 月間アクセス数を40%増加させる
- 資料請求数を月300件まで増やす
- ホームページの直帰率を30%まで下げる
具体的な数字を決めることで、目標を達成するにはどうすればよいか、具体的な施策が考えやすくなります。
さらに、進捗状況を同じように数値化することで、目標に対する達成度合いもわかりやすくなるでしょう。
2.ホームページの現状を分析する
目的や目標を可視化したあとは、今のホームページの状況を分析・可視化します。
状況が可視化できれば、今のホームページで成果が出ない原因がどこにあるかも判断しやすくなります。
状況の分析・可視化を行う方法は、GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを使うのがおすすめです。
- Googleサーチコンソール
-
Googleサーチコンソールは、Googleの検索結果におけるホームページの順位変動や検索キーワードの情報などが分析できるツールです。
キーワードごとの平均検索順位や表示回数、クリック率、被リンクなどがわかります。
- Googleアナリティクス
-
Googleアナリティクスは、ホームページ内のデータを細かく可視化・分析できるツールです。
Webページのアクセス数やユーザーの滞在時間、流入経路、ユーザーの属性(地域・年齢・性別など)などがわかります。
非常に細かい部分まで可視化されるため、Webページ内の問題を分析するのに最適です。
どちらもGoogleアカウントがあれば、誰でも無料で利用できるツールです。
ユーザーがホームページに訪問するまでの状況を分析するならサーチコンソール、訪問後の状況を分析するならアナリティクス、と使い分けましょう。
また、競合他社のホームページと比較してみるのもおすすめです。
競合はどういった部分が優れているか、どういった部分に違いがあるかをチェックすることで、自社ホームページに不足している部分に気づきやすくなります。
WebページのレイアウトやCTAボタンの配置場所、デザイン、商品の価格設定、サービス内容などを中心にチェックしてみましょう。
3.ホームページの改善案を洗い出す
ホームページの可視化や分析を通して、改善案の洗い出しを行います。
目標を達成するには何が不足しているかを考えることで、改善案が出やすくなるでしょう。
たとえば、資料請求の数を月300件まで増やす目標設定をしており、ホームページを分析した結果、CTAボタンを配置している場所があまり読まれていないことがわかりました。
CTAボタンの配置場所に問題があると考えられるため、ホームページの上部に配置する、といった改善案を出します。
このように、分析した情報を基に原因を推測して改善案を考えましょう。
記事の後半では、改善案のアイデアも紹介しているため、なかなかアイデアが出ない方は参考にしてください。
4.改善案に優先順位をつける
改善案を洗い出したあとは、優先順位をつけましょう。
同時に複数の施策を実施するのは、手間とコストがかかります。
また、同時に施策を行うと、効果が出たとしてもどの施策がどの程度効果に影響したかがわかりません。
そのため、改善効果の高そうなものから優先順位をつけ、上から一つずつ施策を行い、結果が出てから次の施策に取りかかるのがおすすめです。
改善効果の高いものとは、直接成果につながる部分や、多くのユーザーに影響のある部分などが挙げられます。
たとえば、問い合わせフォーム、ECサイトのカート機能、アクセス数の多いWebページなどは優先順位を上げるとよいでしょう。
5.改善案を実施し効果検証を行う
実施する改善案が決まったら実行に移し、効果検証を行います。
2~3日後に、一度大きなトラブルなどが起きていないかGoogleアナリティクスなどで確認し、問題がなければ1週間や1か月程度のスパンで数値がどう変化しているか確認しましょう。
改善案が最適だとしても、効果が出るまでに時間がかかるケースも多々あるため、1か月程度は様子を見るのがおすすめです。
もし、数値が悪化しているか変化がないようであれば、改善した部分は元に戻し、次の施策に取りかかりましょう。
改善と効果検証を繰り返すことで、成果を上げるホームページになるのです。
ホームページの改善方法【アクセス数を増やす3選】
ホームページの主な目的である、「アクセス数を増やす」「直帰率・離脱率を下げる」「問い合わせ数を増やす」の3つに分類し、それぞれ具体的な改善方法を紹介します。
アクセス数を増やすための改善方法は次のとおりです。
- 基本となるSEOやMEOを見直す
- SNSや広告などを活用する
- タイトルのクリック率を改善する
基本となるSEOやMEOを見直す
Googleなど検索エンジンからのアクセス数を増加させたいのであれば、SEOやMEOの見直しを行うのがおすすめです。
SEOは「検索エンジン最適化」、MEOは「マップ検索エンジン最適化」を意味する言葉です。
それぞれGoogleやGoogleマップの検索結果などで特定のキーワードが検索されたさい、自社のWebページ・ビジネスプロフィールを上位に表示させるための対策を指します。
Webページのアクセス数は基本的に検索結果の順位表示に比例するため、関連するキーワードに合わせて店舗情報や記事ページを上位に表示できれば、アクセス数も増加できるでしょう。
SEOやMEOは、キーワードをページ内に適切に盛り込むといった内容の対策以外にも、ユーザーの利便性を高めるといった改善方法があります。
たとえば、Webページの表示速度改善や、外部リンクの獲得、スマホなどモバイル端末でのWebページの見やすさなども、改善することでアクセス数が期待できます。
利便性も含めて自社のSEOやMEOの状況を分析し、改善できる部分がないか考えてみましょう。
SNSや広告などを活用する
ホームページへアクセスする経路はGoogleなどの検索エンジン以外にも、SNSや広告など複数存在します。
そのため、検索エンジン以外からのアクセスが少ないようであれば、ほかの経路を強化すればアクセス数の増加が期待できるでしょう。
SNSであれば、企業アカウントを作成してプロフィールにホームページのリンクを貼りつけたり、記事の更新時にお知らせの投稿をしたりすることで、アクセス数を増やせます。
SNSは拡散性も高いため、一気にアクセス数や認知度を高めることも可能です。
また、SNSは種類によっても特徴がある(Instagramは女性が多い、TikTokは10代が多いなど)ため、うまく使い分けることで、コンバージョン率などにもつながりやすくなります。
広告の場合は、リスティング広告を使うと、Googleなどの検索結果の上位に自社ホームページを表示できます。
上位に表示されるものほどユーザーの目に止まりやすくクリックもされやすいため、アクセス数の増加も可能です。
広告は費用がかかるうえ運用も簡単にはできませんが、SEOやMEOと比較すると即時性があり、うまく運用できれば高い効果が期待できるでしょう。
タイトルのクリック率を改善する
タイトルを改善して、クリック率の向上を狙いましょう。
ここで述べるタイトルはタイトルタグ(titleタグ)を指し、Googleの検索結果でテキストリンクとして表示されます。
基本的に検索順位が高いほどクリック率は高い傾向にあり、流入数の増加が期待できます。
しかし、検索回数や競合が多いキーワードで1位になるのはハードルが高いです。
一方、検索回数や競合が多いキーワードで1位を取るより、タイトルの変更でクリック率を改善させるほうが難易度は比較的低いです。
クリック率の向上を意識したタイトルのアイデアを、次にまとめました。
| タイトルのアイデア | 例 |
|---|---|
| 数字の使用で具体性を高める | SEOとは?初心者でも2分で理解できます |
| 6か月で英語がペラペラ話せる方法 | |
| 記号の使用で視認性を向上 | ホームページデザインのトレンド9選【2025年版】 |
| 「アパレル」「ファッション」2つの言葉の違いとは | |
| ターゲットを明確化 | 30代は絶対に読むべき!おすすめビジネス本5冊 |
| 海外旅行が初めての方におすすめの国・地域 | |
| 疑問系でユーザーの好奇心を刺激 | 転職を考えるタイミングはいつ? |
| なぜ日本で物価高が起きている?原因を解説 | |
| 肩書を示して信頼度を高める | 副業の経費計上はどこまで?税理士が徹底解説 |
| 冬の乾燥肌を対策する方法|皮膚科医が教えます |
検索ユーザーが何を知りたいのか考えたうえで、タイトルを作成しましょう。
ホームページの改善方法【直帰率・離脱率を下げる4選】
ホームページの直帰率・離脱率を下げる改善方法は次のとおりです。
- 情報が見やすくわかりやすいレイアウトにする
- グローバルナビゲーションの配置や項目を見直す
- ファーストビューの見直しを行う
- イラスト・図・表でわかりやすく説明する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
情報が見やすくわかりやすいレイアウトにする
直帰率や離脱率を下げるには、レイアウトを改善するのが有効です。
基本的にユーザーは、自分の求めている情報をなるべく早く見たいと思っています。
そのため、ユーザーのニーズが高い情報はなるべくWebページの上部に配置し、すぐ必要な情報へアクセスできるよう動線設計をするのが重要です。
たとえば、カフェのホームページであれば、一般的にコンセプトや売り、メニューなどのニーズが高いため、Webページの上部に表示します。
営業時間やアクセスの方法などは最後に確認する情報のため、ページの下部に表示します。
コンテンツごとにWebページを作成している場合は、各ページの上部にグローバルナビゲーションを置いて、すぐ情報にたどり着けるよう動線設計するのも重要です。
コラム・ブログであれば、記事の全体像をページの上部で説明するとユーザーが知りたい情報があるのかがわかります。
記事にページ内リンクつきの目次を設置するのも、ユーザーが求めている情報がすぐに見つけられるため有効です。
グローバルナビゲーションの配置や項目を見直す
ホームページのグローバルナビゲーション自体に改善の余地があるケースがあります。
グローバルナビゲーションとは、すべてのWebページに共通して設置するリンクです。
主要なリンクがまとめられたメニューであり、クリックすると各Webページへ移動できます。
グローバルナビゲーションは、Webページのスクロールに合わせて追従するように設計するのがおすすめです。
ユーザーがWebページを閲覧している途中でも、すぐに別のWebページへと移動ができるからです。
たとえば、カフェのホームページであれば、メニューを見てカフェに行きたくなり、営業時間やアクセス方法が見たくなった場合、わざわざページのトップへ戻らずとも、すぐにナビゲーションをクリックして該当ページへ移動できます。
ちょっとしたことですが、このように少しでもユーザーの手間を少なくするよう動線を設計することで、回遊性を高めやすくなります。
また、グローバルナビゲーションの項目は、ニーズを反映させましょう。
各Webページの中で特に閲覧数の多いものがあれば、ナビゲーションの項目に加えます。
さらに、ニーズが低く会社側としても重要性が低いWebページをナビゲーションの項目に入れている場合は、思い切って削除するのもおすすめです。
項目数は多すぎると見づらくなり、閲覧が分散することで本当に見てほしいWebページへたどり着かなくなる可能性があります。
全体のバランスを考えつつ、ニーズに即した内容に整理しましょう。
ファーストビューの見直しを行う
ファーストビューとは、ユーザーがホームページにアクセスしたさい、最初に目にする画面部分です。
特にトップページのファーストビューは、ホームページや会社に対する印象が決まる重要な要素であり、しっかりと訴求できなければ離脱につながります。
ファーストビューは、基本的にホームページや企業全体を象徴するような画像を使い、画面いっぱいに画像が映るように配置します。
また、画像の中には商品や企業のアピール文を入れます。
抽象的な文よりも、具体的な数字などを使って強みとなる部分をアピールすることで、閲覧者の興味を引きやすくなるでしょう。
そのほか、各Webページのファーストビューと、トップページのファーストビューはデザインに統一性をもたせることで、情報がスムーズに頭へ入りやすくなります。
イラスト・図・表でわかりやすく説明する
Webページ全体をより見やすくしたいのであれば、イラスト・図・表を適宜使うのがおすすめです。
文章だけのWebページは非常に見づらく、ユーザーは途中で疲れて離脱しやすくなります。
文章だけでは内容をイメージしにくく、商品やサービスの魅力も伝わりにくいでしょう。
そのため、Webページをぱっと見ただけでも内容が理解できるよう、必要に応じてイラスト・図・表を差し込みます。
リソースに余裕があれば、動画を使うのもよいでしょう。
動画は画像以上に多くの情報量を伝えられ、閲覧者の注意を引きやすいため、滞在時間の増加が期待できます。
ホームページの改善方法【問い合わせ数を増やす4選】
ホームページからの問い合わせ数を増やす改善方法は次のとおりです。
- 問い合わせまでの誘導を自然かつわかりやすくする
- 問い合わせボタン・バナーは追従させる
- 問い合わせボタン・バナーを視覚的に目立たせる
- フォームの入力項目を見直す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
問い合わせまでの誘導を自然かつわかりやすくする
問い合わせ数を増やしたい場合は、問い合わせまでの動線をよりわかりやすくするのが重要です。
CTAボタン・ナビゲーション・問い合わせフォームなどを、ユーザーがすぐ気づける場所に配置できているか、どのWebページからでも問い合わせができるか、などをチェックしましょう。
また、ストーリー性を意識して問い合わせまで誘導するのも重要です。
たとえば、建設会社のコラム記事でオフィスの内装工事の料金相場について解説したあと、「企業の規模やニーズによっても料金は大幅に変わるため、事前に見積もりを依頼して正確な金額を知るのが重要」と書いたとします。
文章のあとに、「無料で見積もりをチェック!」といったCTAボタンが配置していれば、ユーザーは『見積もりをお願いしてみようかな』と感じ、ボタンをクリックしてもらいやすくなります。
このように、ページの文脈とCTAボタンやリンクの文言をうまく連動させ、自然な形で誘導できれば、問い合わせ数の増加が期待できるでしょう。
問い合わせボタン・バナーは追従させる
問い合わせ用のCTAボタンやバナーは、追従できる設計にするのもおすすめです。
各WebページにCTAボタンや問い合わせフォームを設置したとしても、場所が固定されていると、ページをスクロールする手間がかかります。
そのため、スクロールしている間に気持ちが変わるなど、取りこぼしが生まれる可能性があります。
しかし、スクロールしてもボタン・バナーが追従し、常に画面へ表示されていれば、興味をもったタイミングですぐに問い合わせへつなげられるのです。
ただし、あまりボタンやバナーのサイズを大きくしすぎると、Webページの閲覧自体の邪魔になる可能性もあるため、全体のバランスを考えて設置しましょう。
問い合わせボタン・バナーを視覚的に目立たせる
問い合わせまでの動線をよりわかりやすくするには、ボタン・バナーを目立たせるのも有効な手段の一つです。
ボタン・バナーを目立たせるには、次のポイントを抑えましょう。
- ホームページのメインカラーと反対の色を使う
- 立体感や影を入れる
- 行動を促すフレーズを入れる
- クリックしやすい大きさ(大きすぎず・小さすぎず)
- 余分な余白は入れず、視覚的なストレスを作らない
行動を促すフレーズでは、「無料・限定・今だけ・◯月末まで」など、今行動することでお得になるような印象を与えるのがおすすめです。
フォームの入力項目を見直す
問い合わせフォームの入力項目も、精査する必要があります。
項目数が多すぎると入力が手間になり、途中で離脱される原因になります。
そのため、入力項目の数はなるべく減らし、必要最低限の情報のみに見直しましょう。
また、記述式の項目も入力の手間がかかりやすく、文章を考える必要もあるため、なるべく選択形式を増やすのがおすすめです。
可能であれば、入力内容のエラー検証を記入した項目ごとに実施し、すぐに修正できる設計にすると利便性が上がります。
まとめ
ホームページ改善のステップや、具体的な改善方法について紹介しました。
ホームページを改善する大まかな手順は、次のとおりです。
| 5つのステップ | 概要 |
|---|---|
| 1.目的・目標を確認 | 全体の方向を定め、具体的な数字で設定する |
| 2.現状を分析する | GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスで現状を可視化 |
| 3.改善案を洗い出す | 原因を推測し、原因を解消するための案を洗い出す |
| 4.優先順位をつける | 施策が多く出た場合は、効果の期待できる順番で順位をつける |
| 5.実行し効果検証を行う | 1つずつ実行し、どの程度効果があったか測定する |
具体的な改善方法を目的別に分けると、次が考えられます。
| 目的別 | 改善方法 |
|---|---|
| アクセス数を増やす方法 | 基本となるSEOやMEOを見直す |
| SNSや広告などを活用する | |
| タイトルのクリック率を改善する | |
| 直帰率・離脱率を下げる方法 | 情報が見やすくわかりやすいレイアウトにする |
| ナビゲーションの配置や項目を見直す | |
| ファーストビューの見直しを行う | |
| イラスト・図・表でわかりやすく説明する | |
| 問い合わせ数を増やす方法 | 問い合わせまでの誘導を自然かつわかりやすくする |
| 問い合わせボタン・バナーは追従させる | |
| 問い合わせボタン・バナーを視覚的に目立たせる |
今回の記事を参考にして、成果の出るホームページを構築しましょう。
また、当サイト「ビズサイ」ではサブスク型ホームページ制作サービスを提供しています。
低コストでオリジナルデザインのホームページを作成しており、公開後も保守管理や更新代行などの手厚いサポートをしています。
ホームページの新規開設やリニューアルでお困りの方は、ビズサイにお任せください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。
まずは無料でご相談ください。
お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。
※年末年始・土日祝は定休日となります
※受付時間 9:00~17:30