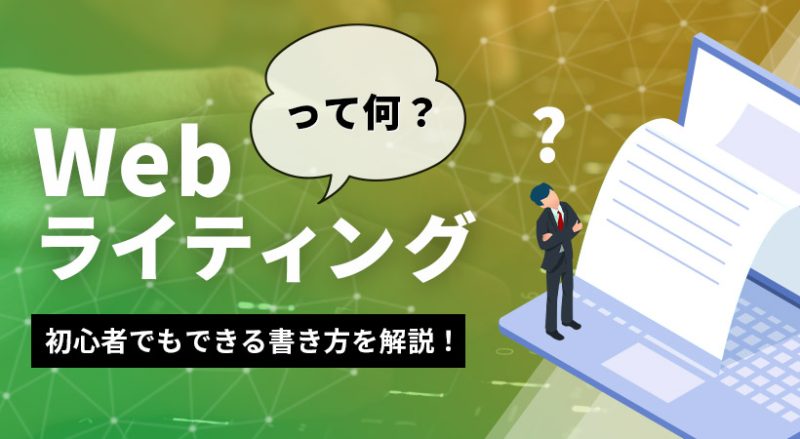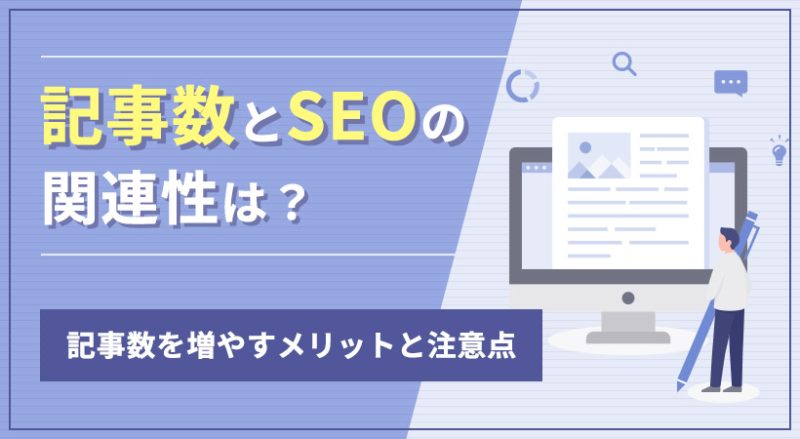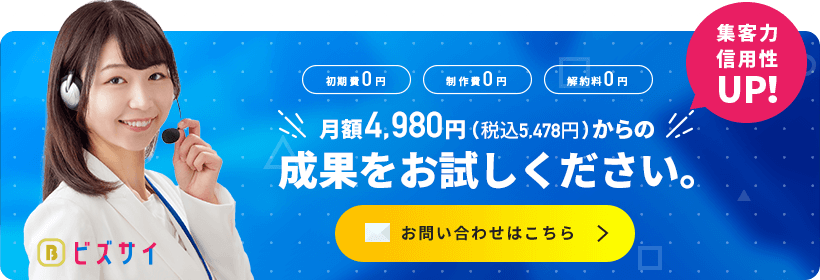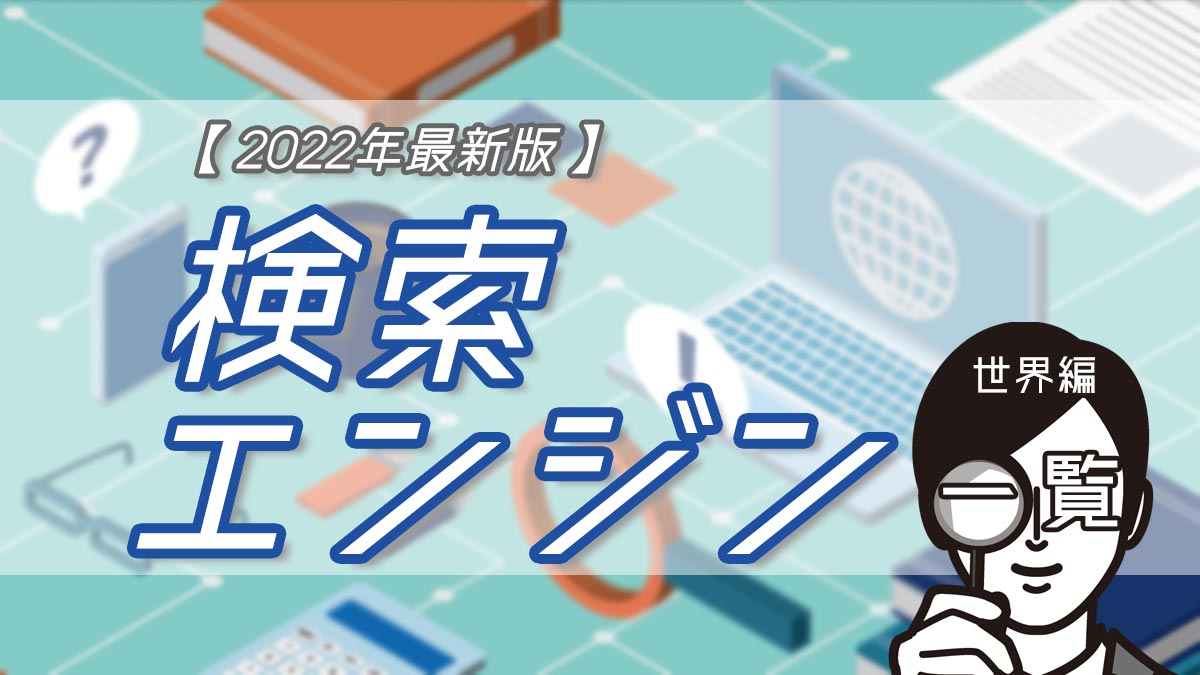ブログ記事のリライトのやり方とは?効果・コツ・注意点・タイミング・方法を解説
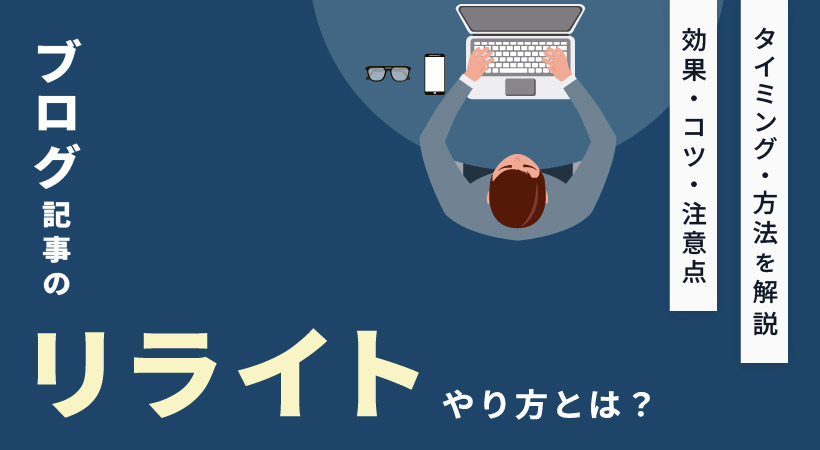
公開したブログ記事の順位が伸び悩んでいたり、情報が古くなったりしているならリライトが有効な手段です。
『既存のブログ記事の内容をリライトして質を高めるには?』
『検索順位が落ちた記事をリライトして改善したい』
『リライトによってアクセス数を増やす方法を教えて』
上記の疑問に答えるため、今回の記事では、リライトの効果・具体的な手順・成果を最大化させるポイントをまとめました。
さらに、リライトに適したタイミングの見極め方や、作業時に陥りやすい注意点についても詳しく紹介します。
本記事を読めば、SEO効果を高めるリライトの正しい知識が身につき、ブログの資産価値を向上させる道筋が明確になります。
まずはリライトがもたらす多様な効果への理解を深め、自分のブログを成長させるための第一歩を踏み出しましょう。
※2025年8月5日:記事の情報を更新しました
ブログに必須の記事のリライトとは?
ブログのリライトとは、公開済みの記事を見直して情報の質・鮮度・網羅性を向上させ、コンテンツ価値を最大化する更新作業です。
単なる誤字脱字の修正ではなく、以下の取り組みがリライトの主な目的となります。
| 目的 | 説明 |
|---|---|
| SEO効果の向上 | 検索順位を上げ、アクセス数を増やすための最適化 |
| 情報の最新化 | 古い情報・リンク・データを最新のものに更新 |
| 読者満足度の向上 | わかりやすく・読みやすくして記事からの離脱を防ぐ |
| 検索意図への最適化 | ユーザーの検索意図により正確に応える構成に変更 |
| 成約率の改善 | 導線・CTAを見直してコンバージョンを高める |
| 表現・文章の改善 | 冗長・曖昧な表現を削除し、読みやすく整える |
Googleの評価基準やユーザーが検索する意図は常に変化するため、公開記事を放置していると徐々に評価が下がる可能性はあります。
そのため、検索順位が伸び悩んでいる記事の構成や表現を再検討し、読者の疑問をより深く解決できる内容に改善しましょう。
ほかにも、「タイトルの修正によるクリック率向上」「コンバージョン率の改善」などもリライトの重要な目的です。
特に検索順位が10位~30位前後で停滞している記事は、リライトによる順位上昇の効果が出やすい傾向にあります。
ブログ記事のリライトで得られる効果
ブログ記事のリライトで得られる効果は、以下のとおりです。
- 検索順位を上げて流入数を増やす
- 情報を最新にしてUXを向上させる
- 記事のクオリティを高めて可読性を上げる
- コンバージョン率を改善する
リライトを通じて得られるさまざまな効果を理解し、ブログの価値を最大限に高めるために改善していきましょう。
検索順位を上げて流入数を増やす
ブログ記事を定期的にリライトすると、検索エンジンの評価を高め、検索順位を大きく引き上げる効果が期待できます。
「情報を最新にする」「検索意図に合せたキーワードを盛り込む」などが、検索エンジンから高く評価される傾向にあるからです。
検索エンジンに評価されやすいリライトの傾向について、以下の表にまとめました。
| 評価されやすい要素 | 概要 |
|---|---|
| 情報の更新 | 最新の統計・制度・サービス情報を反映させる |
| 検索意図への対応 | キーワードや内容を検索ニーズの変化に合せて調整 |
| E-E-A-T強化 | 経験・専門性・権威性・信頼性を高める内容を追加 |
| 網羅性の補完 | 競合比較により不足情報や関連トピックを加筆 |
| ユーザー満足の向上 | 正確・包括的な内容で読者の信頼と評価を得る |
たとえば、「最新の統計データや研究結果を追記」「新しいサービスや法律の変更点を反映」といったリライトはよく行われます。
また、競合の上位サイトを分析し、記事に不足しているトピックや解説を補完する作業もユーザー体験の向上には重要です。
情報を最新にしてUXを向上させる
記事の情報を新しく更新するリライトは、ブログの満足度や信頼感といったユーザー体験(UX)を直接的に向上させます。
古い情報や誤ったデータの掲載は、「読者への不利益」「ブログの専門性や信頼性を損なう」などを引き起こすからです。
読者が追い求めるのは正確な情報であり、期待に応える姿勢がブログの評価を高め、ファンを増やす第一歩になります。
情報を最新にするリライトの具体的な作業は、以下のとおりです。
- 記事内で引用している統計データの発表年を確認し、より新しいデータに差し替える
- リンク切れを起こしている外部サイトのURLを修正する
- 紹介している商品やサービスの仕様変更や料金改定を反映させる
読者からの信頼感を醸成するため、公開済みの記事も定期的に見直し、情報の鮮度を常に高く保つ運用を心がけましょう。
記事のクオリティを高めて可読性を上げる
文章表現を磨き、コンテンツの質を高め、可読性の向上によって読者が内容を理解しやすくなるようリライトしましょう。
「誤字脱字の修正」「専門的でわかりにくい表現を平易な言葉へ置き換え」などで、文章をより洗練させるのが大切です。
読者が閲覧を中断してしまう原因の多くは、「冗長な文章」「内容のわかりにくさ」「論理的なつながりが悪い」などになります。
記事のクオリティを高めて可読性を上げるためには、以下の文章ルールを守るのがおすすめです。
| ルール | 概要 |
|---|---|
| 一文は60文字まで | 長文は避けて一文は60文字前後を目安にする |
| 主語と述語の対応 | 主語と述語の関係を明確にする |
| 指示語の多用を避ける | 「これ・それ」などは具体的に言い換える |
| 接続詞を適切に使う | 文同士の関係を明確にする |
| 箇条書き・表の活用 | 複数項目は箇条書き・表にして視認性を高める |
| 漢字とひらがなのバランス | 難読語はひらがなを使い、読みやすさを確保 |
| 適切な改行 | 意味の区切りで段落を分ける |
| 専門用語に補足をつける | 初見の読者でも理解できるようにする |
| 図・画像の活用 | 図・画像で視覚的な理解を助ける |
読者に読みやすくわかりやすい記事にするため、時間をおいてから読み返し、文章を磨き上げる習慣をつけましょう。
コンバージョン率を改善する
リライトは、商品購入や資料請求につながるコンバージョン率(CVR)を改善するための強力な手段です。
読者が記事を読んで満足するだけでなく、行動に移してもらうためには、明確な導線設計と説得力のある情報提供が必要となります。
リライトでコンバージョン率を改善するための方法について、以下の表にまとめました。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 明確なCTA設置 | 誘導ボタン・リンクを目立つ位置に配置 |
| 信頼性の強化 | 実績・口コミ・第三者評価を掲載 |
| 導線の最適化 | 申し込み・購入までの流れを簡潔に整理 |
| ターゲットの明確化 | ペルソナに合せた訴求内容に調整 |
| ランディング要素の強化 | ファーストビューに魅力を集中させる |
| ベネフィットの訴求 | 読者が得られる具体的なメリットを強調 |
また、リライト後はABテストを通じてコンバージョン率を計測し、PDCAサイクルを回して改善を心がけましょう。
ブログ記事のリライトに適したタイミング
ブログ記事のリライトに適したタイミングは、以下のとおりです。
- ブログに一定の記事数が溜まってから開始
- インデックス・評価後の3か月~6か月が目安
- Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て判断
- アルゴリズム更新などの外部要因の発生時
- 記事の情報が古い
適切なタイミングでリライトを実施し、少ない労力で効率的にブログの成果を向上させる必要があります。
ブログに一定の記事数が溜まってから開始
リライトする最適なタイミングは、ブログに30記事~50記事程度のコンテンツが蓄積されてからです。
記事数が少ない初期段階では、既存記事を改善するよりも、新しい記事を作成して情報量を増やす作業が優先されるためです。
また、ある程度のコンテンツ量がなければ、どの記事をリライトすれば効果的か判断するための十分なデータを収集できません。
くわえて、執筆過程でライティングスキルも向上するため、過去の記事を見返したときに改善点がより明確にわかるようになります。
ブログを始めたばかりの段階では、新規記事の作成に集中し、コンテンツ量が増えてからリライトに取り組みましょう。
インデックス・評価後の3か月~6か月が目安
公開した記事をリライトするタイミングは、投稿してからおよそ3か月~6か月後が目安の一つとなります。
公開された記事が検索エンジンに認識され、検索順位などの評価が安定するまでには一定の期間を要するからです。
もし、公開後すぐにリライトを行っても、まだ記事の評価が固まっていないため、リライトの効果を正しく判断するのは困難です。
3か月~6か月ほど時間をおくと客観的なデータが十分に集まり、的確な改善策を立てられるようになります。
Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て判断
リライトのタイミングは、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールを分析し、判断するのが効果的です。
分析ツールを活用すれば個人の感覚に頼らず、具体的な数値データを根拠にして改善すべき点を客観的に特定できるからです。
たとえば、分析ツールでリライトが必要だと判断される主なケースを以下の表にまとめました。
| 指標・状況 | リライト判断の根拠 |
|---|---|
| 表示回数が多いのにクリック率が低い | タイトルやディスクリプションの改善が必要 |
| 検索順位が低下している | 競合に劣る内容・情報の古さが原因の可能性がある |
| 滞在時間が短い | 内容が検索意図に合っていない |
| 離脱率・直帰率が高い | 読みにくさ・導線の不備・期待外れの内容 |
| 特定キーワードの流入が少ない | キーワードの最適化が不十分 |
| コンバージョンが発生していない | 記事の訴求力やCTAの弱さが疑われる |
| インデックス登録されていない | 技術的問題またはコンテンツの質に課題あり |
どの程度、記事の内容をリライトするかは、分析ツールのデータに基づき適切に判断する必要があります。
たとえば、「表示回数が多いのにクリック率(CTR)が低い」だけなら、訴求力のあるタイトルに変更するだけでも効果を期待できます。
一方、検索順位が低い場合はコンテンツの質が問題だと考えられますので、全面的なリライトも含めて検討しましょう。
アルゴリズム更新などの外部要因の発生時
Googleのコアアルゴリズムアップデートや、関連する法律・制度の変更も、記事をリライトする重要なタイミングです。
コアアルゴリズムアップデートとは、Googleが検索アルゴリズムやシステムを見直して大規模に変更するもので、検索順位が大幅に変動します。
そのため、大規模なアップデート後には、上位表示されていた記事の順位が大幅に下落してしまうケースも多いです。
アップデートに起因する順位下落は、既存の記事が新しい評価基準を満たせなくなったのが原因と考えられます。
そのため、順位が下落した原因を分析し、新しい評価基準に適応させるためのリライトが不可欠となります。
また、法律や制度に関連するコンテンツの場合、変更があったときには最新情報にキャッチアップするようにしましょう。
記事の情報が古い
記事で扱っている商品・サービス・関連する法律などの情報が古くなってしまった場合は、速やかにリライトを行うべきです。
古い情報の放置は読者からの信頼を失う原因になるだけでなく、検索エンジンからの評価が低下する可能性もあります。
特に「統計データ」「法律」「紹介しているサービスの料金プラン」などは、時間の経過とともに変わりやすい項目です。
読者は常に最新の正確な情報を求めているため、コンテンツの鮮度を高く保つ運用は、ユーザー体験の向上につながります。
記事の情報の鮮度を保つためには、更新リマインダーを設定できる以下のWordPressのプラグインがおすすめです。
| プラグイン名 | 主な機能 |
|---|---|
| Content Reminder | 投稿・固定ページが指定した日数(デフォルト90日)未更新になると、ダッシュボードウィジェットで一覧表示し、メール通知も実行 |
| Reminders Add-on – Better Notifications for WP | 「Better Notifications for WP」の拡張機能で、投稿・ページ・カスタム投稿が設定期間更新されないと、指定ユーザーやロールにメールリマインダーを送信 |
初心者にもできる!SEO効果を高めるブログ記事のリライトのやり方
SEO効果を高めるブログ記事のリライトのやり方は、以下のとおりです。
- リライト対象記事の分析と選定
- 検索意図・関連キーワードの再分析と記事構成の見直し
- E-E-A-Tと独自性の強化
- UX・ユーザビリティの向上
- タイトル・メタ情報の見直しと変更
- カニバリゼーション記事の非公開・統合
- アクセス解析とPDCAサイクル
正しい手順に沿ってリライトを進め、検索エンジンと読者の双方から評価されるブログ記事を目指しましょう。
リライト対象記事の分析と選定
効果的なリライトの第一歩は、改善の見込みが高い記事を正しく見極めて、優先順位をつけて選定する作業から始まります。
闇雲に修正するのではなく、ポテンシャルを秘めた記事にリソースを集中させるのが、SEO効果の最大化に効率的だからです。
リライトで効率的に効果を得られる可能性が高いブログ記事の状況を、以下の表にまとめました。
| ケース | 優先理由 |
|---|---|
| 検索順位が下落している記事 | 流入減の主因となるため、緊急対応が必要 |
| 情報が古い記事 | 誤情報のリスクがあり、信頼性を損なう |
| クリック率が低い記事 | タイトル・見出し改善で即効性が見込める |
| 競合に負けている記事 | 上位記事との差分を埋めれば改善の余地が大きい |
| アクセス数は多いがCVRが低い記事 | 導線の再設計で成果を得やすい |
| 流入数が多いが滞在時間が短い記事 | 内容の質や構成に課題がある可能性大 |
| 検索順位が11位~30位の記事 | リライトによって上位表示が狙いやすい |
Googleサーチコンソールなどの分析ツールを活用し、客観的なデータに基づいてリライト対象の記事を選定しましょう。
検索意図・関連キーワードの再分析と記事構成の見直し
記事を選定したあとは、関連キーワードから検索ニーズを徹底的に再分析し、記事全体の構成を見直しましょう。
SEO記事における「検索ニーズを満たす」とは、ユーザーが抱える課題を解決するための情報の提供を指すケースが大半です。
まずは対象のキーワードを検索し、上位表示されている競合サイトがどのような情報を提供しているかを詳細に分析します。
さらに、関連キーワード・再検索キーワードを調査し、見出しに盛り込む形で新しい構成案を作成してください。
なお、関連キーワードは「Ubersuggest」「ラッコツールズ」、再検索キーワードは「GetKeyword」で調査できます。
E-E-A-Tと独自性の強化
Googleに評価されるためにはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の担保と、独自性のある記事が必要です。
Googleは記事の信頼性を重視しており、二次情報のまとめ記事などに基づいたコンテンツは順位が下がる可能性があります。
記事の信頼性を担保するために考えられる方法を、以下の表にまとめました。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 執筆者情報の明示 | 経歴・専門性を記載し、信頼感を高める |
| 出典の明記 | 公的機関・一次情報を引用し、裏付けを示す |
| 最新情報の反映 | データ・制度・ニュースを常に更新 |
| 専門家の監修 | 有資格者の監修で内容の正確性を補強 |
| 体験・実績の記述 | 実際の経験や事例を交えて説得力を高める |
また、同じ情報でも切り口や見せ方によって、自分のブログ独自のコンテンツになるケースも多々あります。
UX・ユーザビリティの向上
「求める情報を見つけやすい」「快適に読み進められる」といった、UX(ユーザー体験)とユーザビリティの向上が大切です。
コンテンツ内容が優れていても、読みにくく使いにくいブログは読者の離脱につながり、検索エンジンからの評価も低下します。
「記事中に図やイラストを挿入する」「適度な改行」「箇条書きを用いて見やすくする」などの工夫を行いましょう。
また、スマートフォンでの閲覧時に文字が小さすぎたり、表示が崩れたりしないかを確認するのも必須の作業です。
くわえて、表の利用時はスマートフォンでも見やすいよう、「2列程度にする」「横スクロールしやすくする」などもおすすめです。
タイトル・メタ情報の見直しと変更
記事の内容を的確に表し、検索結果でユーザーの目を引くように、記事タイトルとメタディスクリプションの見直しを行いましょう。
タイトルは検索順位やクリック率に直接影響する重要な要素で、つけ方によって大きくアクセス数が変わります。
タイトルの基本的なつけ方について、以下の表にポイントをまとめました。
| ルール | 概要 |
|---|---|
| 左側にキーワードを配置する | できるだけキーワードは左側に配置し、検索意図と一致させて上位表示を狙う |
| 読者のメリットを明示 | 得られる効果や解決できる悩みを示す |
| 数字を使う | 「〇選」「〇つの方法」などで具体性を出す |
| 興味を引く表現を使う | 驚き・共感・意外性でクリック率を上げる |
| 30文字前後 | 公式発表ではないが、検索結果で見切れない文字数 |
| タイトルと内容の整合性を保つ | クリック後の期待外れを防ぎ、直帰を抑える |
キーワードを左側に配置するのは、読まれる文字列の最初のほうに含めておき、目当ての情報だとユーザーに感じさせるためです。
また、記事の要約であるメタディスクリプションも、ユーザーが求めている情報があると端的に示す必要があります。
カニバリゼーション記事の非公開・統合
選定のミスで、複数の完全一致・類似したキーワードがある場合、ブログでカニバリゼーションが起きている可能性が高いです。
カニバリゼーションとは、同一のブログ内で類似する複数のページが競合し、検索順位が分散・低下してしまう現象です。
そのため、複数の完全一致・類似したキーワードの記事を分析し、成果の低いコンテンツを非公開にしましょう。
なお、非公開や削除にした記事から301リダイレクトを行い、一つのコンテンツに検索エンジンの評価を集中させてください。
なお、最初のキーワード選定時から、できる限りカニバリゼーションを起こさないよう注意するのがベストの対応です。
アクセス解析とPDCAサイクル
リライトは実行後に効果をGoogleアナリティクス・サーチコンソールでしっかりと測定し、改善を繰り返すのが成功の鍵です。
一度のリライトで必ずしも結果が出るとは限らないため、データに基づいた客観的な評価と継続的な改善活動が必要だからです。
リライトを実施したあとは、Googleサーチコンソールで検索順位やクリック率の変動を定期的にチェックしましょう。
順位が思うように上がらないときは原因を再度分析し、次の改善アクションへとつなげていく必要があります。
ブログ記事のリライトにおけるコツ・注意点
ブログ記事のリライトにおけるコツ・注意点は、以下のとおりです。
- URLはできるだけ変更しない
- リライトの目的とターゲットを明確にする
- 上位表示されている記事のリライトは慎重に行う
- 内部リンク・メタ情報構造は慎重に扱う
- 短期間でリライトを繰り返さない
注意点を押さえてリライトのリスクを回避し、安全かつ効果的にブログ記事の価値向上を目指しましょう。
URLはできるだけ変更しない
ブログをリライトするときに、記事のURLを変更しないのが最も大切な注意点です。
URLを変更すると、蓄積されてきた検索エンジンからの評価や外部サイトからの被リンクがすべてリセットされます。
GoogleはURLが変わると新しいWebページとして認識するため、評価ゼロからのスタートとなる危険性が非常に高いです。
301リダイレクトで転送しても評価が完全に引き継がれる保証はなく、手間がかかるだけで変更のメリットはほとんどありません。
WebサイトのリニューアルでURL構造を変更するなど、特別な理由がない限りは、記事のURLはできるだけ変更しないようにしましょう。
リライトの目的とターゲットを明確にする
作業前には、「何のためにリライトするのか」という目的設定と、「誰に届けたいのか」というターゲットの明確化が不可欠です。
主に設定されるリライトの目的について、以下の表にまとめました。
| 目的 | 概要 |
|---|---|
| 検索順位の向上 | 上位表示を狙い、自然検索からの流入を増やす |
| 情報の最新化 | 古い内容を更新し、正確性を保つ |
| クリック率の改善 | タイトルや説明文を見直してクリック率を上げる |
| 滞在時間の向上 | 読みやすく構成し直して離脱を防ぐ |
| コンバージョン率の改善 | 訴求や導線を最適化して成約につなげる |
目的設定後にターゲットユーザーを改めて定義すれば、コンテンツの改善方向が定まり、一貫性のあるリライトが可能になります。
上位表示されている記事のリライトは慎重に行う
すでに検索結果で上位表示されている記事は、順位下落のリスクを伴うため、非常に慎重な対応が求められます。
そもそも、検索上位に表示されているブログ記事に対しては、「リライトしない」といった選択肢も考慮しましょう。
特に記事の主題を大きく変えるような構成の変更や、タイトルの全面的な書き換えはおすすめできません。
「古くなった情報の更新」「誤字脱字の修正」といった、現在の評価を維持するための最小限の変更に留めるのが賢明です。
検索10位以内ならリライトはできるだけ控え、11位以下に落ちてから初めてリライトを検討するのが無難な対応です。
内部リンク・メタ情報構造は慎重に扱う
リライトを行うときには、構成・内部リンク・メタディスクリプションなどを維持すべきケースも見受けられます。
たとえば、検索順位が11位~30位など比較的上位の場合、それなりの評価をGoogleから受けていると考えられます。
そのため、記事の悪い部分のみ変更し、良いところはそのまま維持してリライトするのが無難な方法です。
また、内部リンク構造についてもできる限り維持し、ブログ記事の評価が落ちないように細心の注意を払いましょう。
ただし、以下のようなケースでは構成やメタディスクリプションを一新したほうがよいと判断されます。
- 検索順位が30位以下と非常に低い
- 構成で関連・再検索キーワードが盛り込まれていない
- 検索ニーズが捉えられていない
- 文章のクオリティが著しく低い
- 文章量に対する情報量が非常に少ない
- タイトルのつけ方が読者の関心を引かない
短期間でリライトを繰り返さない
一度リライトを行った記事は効果を判断するために数か月ほどおいて、短期間で何度も修正を繰り返さないでください。
リライトによる変更が検索エンジンに認識されて、評価として検索順位に反映されるまでには相応の時間がかかるためです。
また、リライト直後に焦って再修正を重ねてしまうと、どの施策が有効だったのかを正確に分析できません。
最低でも数週間以上は順位の変動を観察し、Googleが変更点を再評価するのを待つ忍耐が成功の鍵となります。
ブログ記事のリライトに関するよくある質問
ブログ記事のリライトに関するよくある質問は、以下のとおりです。
- ブログ記事のリライトで順位が下がったらどうしたらよい?
- ブログ記事をリライトしていつごろ効果が現れる?
- ほかのブログの記事のパクリで順位は上がる?
- ブログ記事のリライトは初心者には難しい?
あらかじめリライトの疑問や不安を解消し、初心者でも安心して記事の改善作業に取り組める準備を整えましょう。
ブログ記事のリライトで順位が下がったらどうしたらよい?
リライト後に検索順位が下がった場合、まずは慌てずに様子を見て、そのうえで原因を分析して対処する必要があります。
検索エンジンがリライト後のコンテンツを再評価するには時間がかかり、一時的な順位変動は頻繁に起きるからです。
1か月ほど順位が回復しない場合、ユーザーの検索意図から内容がずれている可能性を疑いましょう。
また、「タイトルの大幅な変更」「不適切な内部リンクの挿入」などが原因となるケースも考えられます。
原因の特定が難しく、順位の下降が続くようであれば、リライト前の状態に戻して再度分析からやり直すのが賢明です。
ブログ記事をリライトしていつごろ効果が現れる?
リライトしてからSEO効果が現れるまでの期間は、一般的に1か月~3か月程度を目安と考えるのが妥当です。
ブログ全体の評価が高い場合や、競合が少ないキーワードであれば、数週間ほどで順位が上昇するケースもあります。
一方、「競争の激しいキーワード」「ドメインパワーが弱い」といった場合は、半年以上かかるケースも珍しくありません。
ほかのブログの記事のパクリで順位は上がる?
ほかのブログ記事をコピペした「パクリ」行為で作成したコンテンツでは、検索順位が上がる見込みはほぼありません。
むしろ、Googleから重大なペナルティを受けて、SEOで大きなマイナスとなるリスクが非常に高いため絶対にやめましょう。
Googleからコピーコンテンツと判断された場合、該当記事の順位が上がらないだけでなく、ブログ全体の評価が下落します。
くわえて、最悪の場合はインデックスから削除されるなど極めて厳しい措置が執られてアクセスが激減するリスクが大きいです。
何かの間違いで検索上位に表示されたとしても、権利者から以下の対処をされるとペナルティを受けます。
- 権利者がGoogleに著作権侵害による削除リクエストを申請する
- 権利者が損害賠償を請求する
なお、削除リクエストが認められると該当記事はインデックスから削除され、検索結果に表示されなくなります。
ブログ記事のリライトは初心者には難しい?
ブログ記事のリライト自体は、正しい手順とポイントを理解すれば、初心者でも十分に実践できる作業です。
ただし、リライトによって検索エンジンでの上位表示などの結果を出すには、さまざまなノウハウとスキルが必要となります。
そのため、最初から完璧なリライトを目指すのではなく、読者にとって少しでも読みやすくなるよう改善する姿勢が大切です。
「関連・再検索キーワード調査」「検索ニーズの分析」「リサーチスキル」などを身につけ、良質なコンテンツを作成しましょう。
まとめ
ブログのリライトは公開済み記事の情報の鮮度や網羅性を高め、コンテンツの価値を最大化させる重要な更新作業です。
SEO効果による検索順位の向上はもちろん、読者の満足度やコンバージョン率の改善にも直接つながるのがリライトです。
分析ツールで客観的データに基づき対象を選定し、検索意図を再分析して構成を見直す手順が成功の鍵となります。
リライト時には絶対にパーマリンクを変更せず、すでに上位の記事は順位下落リスクを避けるため慎重に対応してください。
正しい手順と注意点を踏まえて、ブログの資産価値を長期的に高めるために定期的なリライトを実践しましょう。
まずは無料でご相談ください。
お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。
※年末年始・土日祝は定休日となります
※受付時間 9:00~17:30