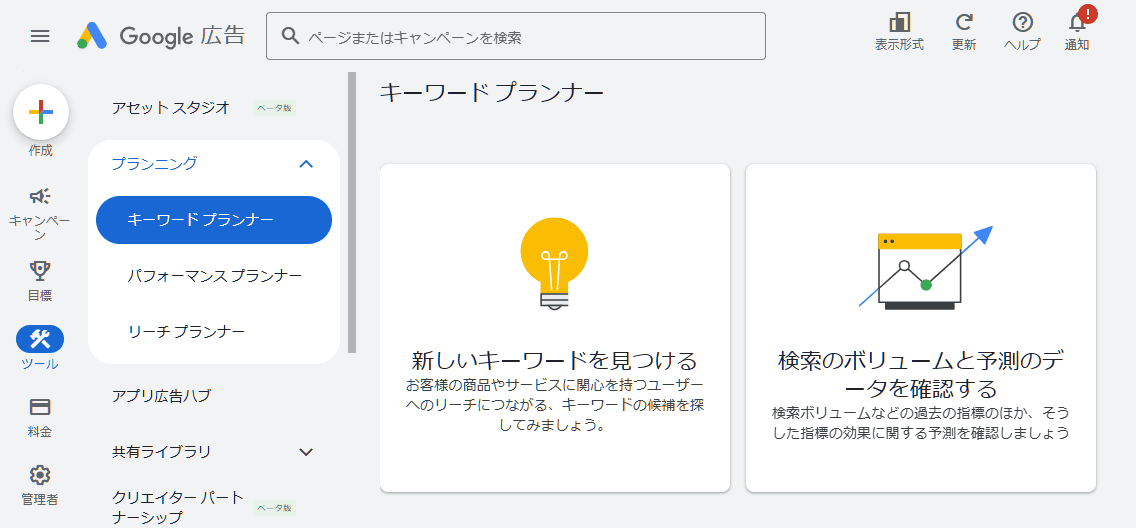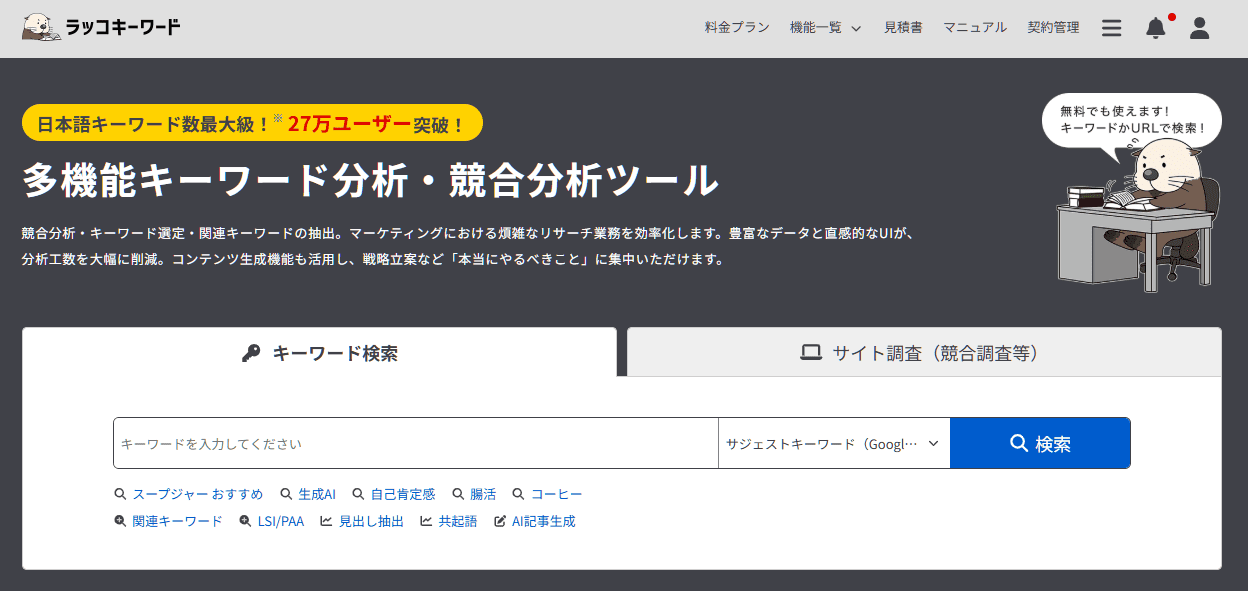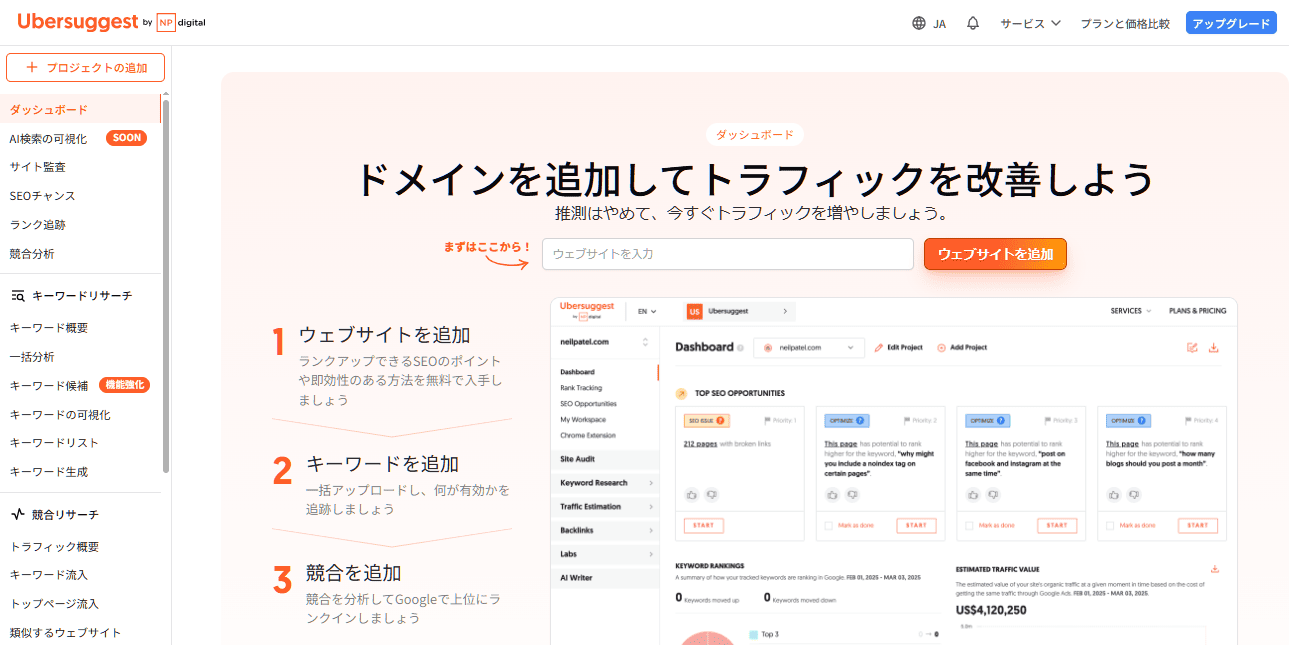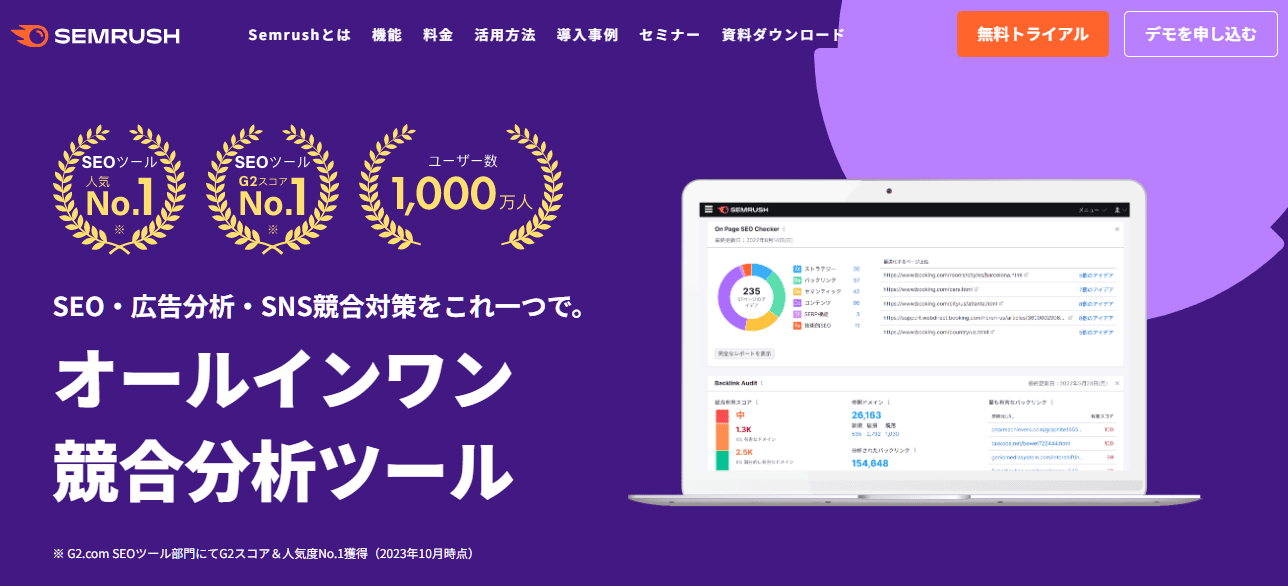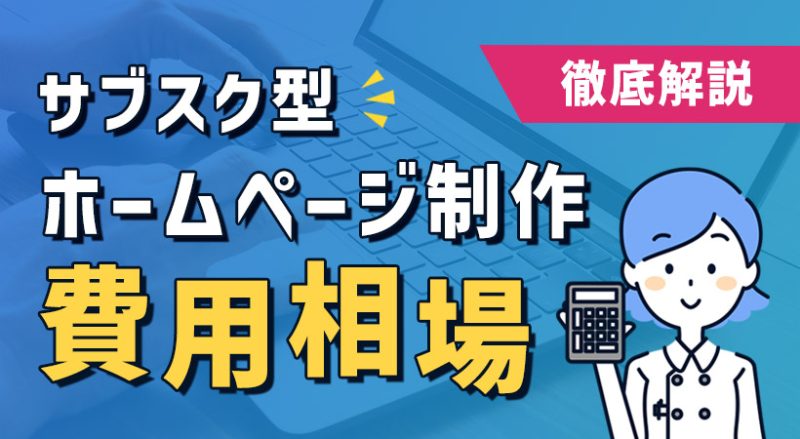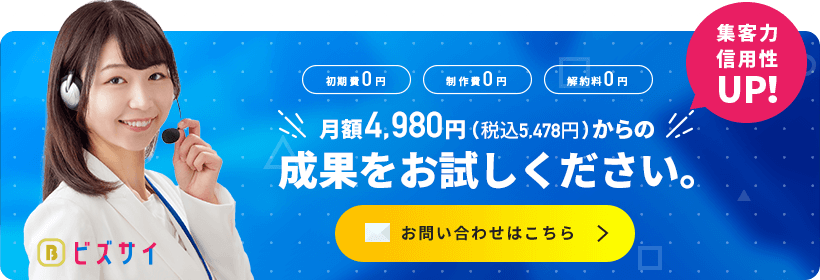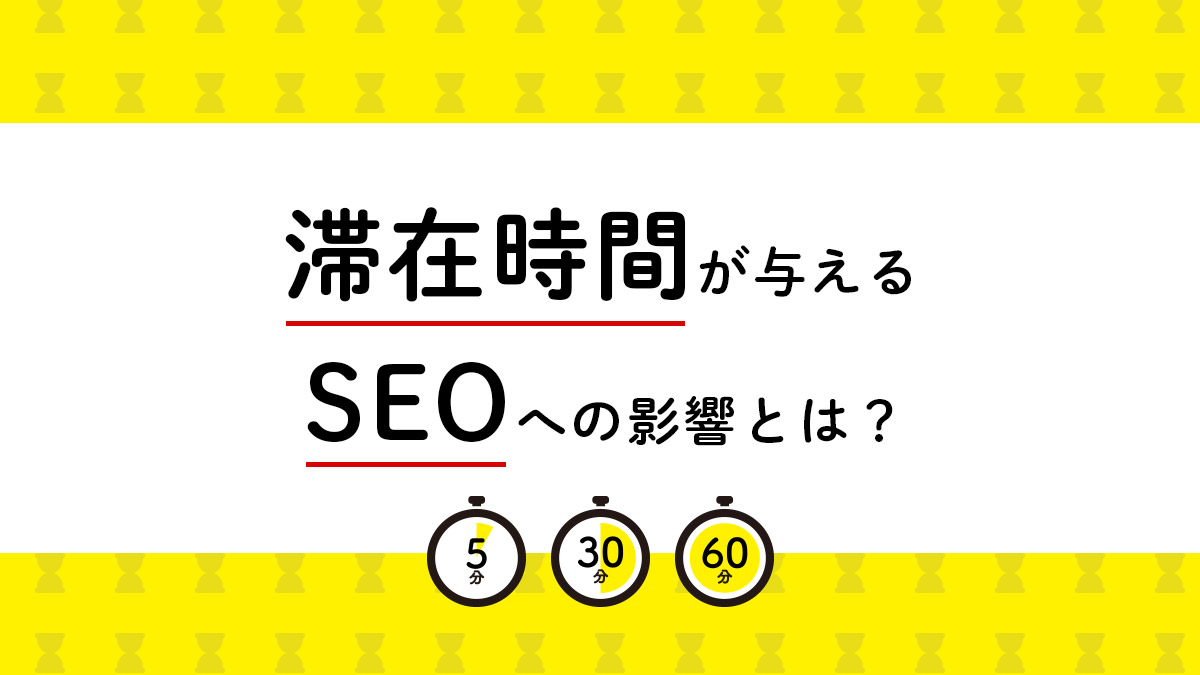SEOのキーワード選定のやり方を初心者向けに解説【選び方・入れ方・分析方法】

Webサイトの集客力を高めたいと考えつつも、肝心なSEOのキーワード選定で悩んだりつまずいたりする人は多くいます。
『自社サイトに適したSEOキーワードを調べたい』
『検索上位を狙える効果的なキーワードを見つけたい』
『競合サイトが使っているキーワードを把握したい』
上記の疑問に答えるため、今回の記事では、キーワード選定の基本的な考え方・手順・注意点までを具体的かつ詳しくまとめました。
さらに、キーワード選定に役立つツールや、選んだキーワードを記事へ反映させる方法についても紹介します。
本記事を読めば、感覚に頼らないデータに基づいたキーワード選定の技術が身につき、集客改善への道筋が明確になります。
まずはキーワード選定の全体像を把握し、自社サイトで成果を得るための着実な第一歩を踏み出しましょう。
※2025年10月2日:記事の情報を更新しました
初心者向け!SEO対策におけるキーワードとは
SEO対策におけるキーワードとは、ユーザーが疑問や課題を解決する目的で検索窓に入力する具体的な単語やフレーズを指します。
Webサイトのタイトルや本文中にキーワードを適切に盛り込むと、検索エンジンにページ内容を明確に伝えられます。
検索エンジンは入力された語句と関連性が高いページから順に、検索結果として表示する仕組みだからです。
たとえば、「ノートパソコン おすすめ 大学生」と検索する人は、大学生活に適した製品の具体的な情報を探しています。
検索意図に応えるため、キーワードに沿って性能・価格・携帯性などを比較するコンテンツを作れば発見されやすくなります。
キーワードはユーザーの検索意図を映し出す鏡であり、ニーズがあるコンテンツを作り出すための出発点です。
SEOでキーワードが重要である理由
SEOでキーワードが重要である理由は、以下のとおりです。
- 検索エンジンでの上位表示に不可欠
- ターゲットユーザーへのアプローチ
- クリック率の向上
- コンテンツの方向性の明確化
- 競合を分析して差別化
上位表示や集客といったキーワードの役割を深く理解し、成果につながるSEO戦略の土台となるポイントを押さえましょう。
検索エンジンでの上位表示に不可欠
キーワードはGoogleなどの検索エンジンがWebページを高く評価し、検索結果の上位に表示させるために不可欠な要素です。
検索エンジンはクローラーというプログラムで世界中のWebページを巡回し、どんな情報が書かれているかを読み取っています。
読み取った情報をデータベースに登録されるのを「インデックス」と呼び、内容が評価されてランキングが決まります。
Webページに含まれるキーワードや関連語が、インデックスの過程でコンテンツのテーマを判断する重要な手がかりとなるのです。
ユーザーが検索するキーワードがタイトルや本文中になければ、検索エンジンは有力な候補としてWebページの認識や評価しにくいです。
ターゲットユーザーへのアプローチ
キーワードは、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性が高いターゲットユーザー層へ訴求できる有効な手段となります。
ユーザーが用いるキーワードの背景には、知りたい・行きたい・したい・購入したいなどの検索意図が隠されているからです。
たとえば、「表参道 美容室 髪質改善」と検索するユーザーは、特定地域で髪の悩みを解決したいと考えている理想的な見込み客です。
顧客となりうる人物像を詳細に設定し、その人がどんな言葉で検索するかを掘り下げれば、成約に近いユーザーとの接点を作れます。
より成果につながりやすいユーザーと出会うため、まずは顧客となりうる人物像について深掘りしてみましょう。
クリック率の向上
タイトルや説明文にキーワードを戦略的に含めると、ユーザーの目に留まりクリック率の向上につながります。
ユーザーは検索結果で、自分が入力したキーワードが太字で強調されている箇所を無意識に探す傾向があるからです。
強調表示を見つけると「求める答えがありそうだ」と瞬時に判断し、クリックする確率が高まる傾向にあります。
効率的に答えを見つけたいというユーザーのニーズは強く、キーワードはクリックを喚起する強力なトリガーとして機能します。
競合サイトの中から自社を選んでもらうためにも、検索意図を的確に反映したキーワードをタイトルなどに盛り込みましょう。
コンテンツの方向性の明確化
対策キーワードを事前に決める作業は、作成するコンテンツが「誰のどんな課題を解決するのか」という方向性を定める設計図です。
キーワードを選定して検索意図を深掘りすると、含めるべき情報の優先順位・解説の切り口・記事全体の構成が明確になります。
一例を挙げると、「法人向け クラウドストレージ 比較」なら、料金やセキュリティなどの具体的な比較項目の網羅が必要です。
キーワードを軸とすると、執筆者の主観による内容のぶれを防ぎ、ユーザーが求める情報を提供できるコンテンツが生まれます。
執筆中にコンテンツの方向性がぶれて迷走しないよう、キーワードを軸とした制作工程を確立しましょう。
競合を分析して差別化
競合サイトがどんなキーワードでどのコンテンツを上位表示させているかの分析は、自社が市場で勝ち抜くための戦略に不可欠です。
獲得しているキーワードの検索量や難易度を把握すれば、競合サイトのコンテンツが満たせない情報の隙間を見つけられます。
たとえば、競合が機能の網羅的な紹介に留まるキーワードに対し、導入事例や顧客インタビューを盛り込めば差別化できます。
また、競合の強みと弱みを冷静に分析し、自社ならではの専門性を発揮できる領域やキーワードを見つけましょう。
SEOのキーワード選定でよく使う基本的な用語
SEOのキーワード選定を効果的に進めるうえで、いくつかの基本的な用語を理解しておく必要があります。
よく使われるSEOにおけるキーワード関連の用語を、以下の表にまとめました。
| 用語 | 詳細 |
|---|---|
| 検索ボリューム | 検索エンジンで特定のキーワードが一定期間に検索される回数 需要の大きさを示す指標 |
| キーワード難易度 | 特定のキーワードで上位表示を獲得する難しさを数値化したもの 競合の強さや被リンク数などを基準に算出される |
| ロングテールキーワード | 検索回数は少ないが、複数語で構成される具体的な検索クエリ 競合が少なく、成約率が高い傾向がある |
| サジェストキーワード | 検索エンジンが検索補助として提示する関連候補キーワード ユーザーの関心や検索行動を反映している |
| 関連キーワード | 検索クエリと関連性が高いと検索エンジンが判断するキーワード ユーザーの潜在ニーズを把握する手がかりになる |
| 再検索キーワード | 初回検索のあとにユーザーが追加で入力するキーワード 検索意図の深掘りや絞り込みを示す |
| トランザクショナルキーワード | 「購入する」「申し込む」など、ユーザーが行動・取引を意図して検索するキーワード |
| インフォメーショナルキーワード | 「方法」「とは」など、情報収集を目的とした検索で使われるキーワード |
| ナビゲーショナルキーワード | 「Amazon」「楽天ログイン」など、特定のWebサイトやブランドにアクセスする目的で検索されるキーワード |
| 検索意図 | ユーザーが検索する目的を分類する概念 主にインフォメーショナル・ナビゲーショナル・トランザクショナルに区分される |
SEOにおいて重要な検索意図とは、「なにが知りたいか」「どのような課題を解決したいか」です。
検索する理由はなんらかの課題を解決したいからであり、検索意図に応えるコンテンツこそが検索エンジンから評価されます。
SEOにおけるキーワードの種類
SEO戦略を構築するうえで、キーワードは特性に応じていくつかの種類に分類できると理解しておきましょう。
キーワードの分類は主に月間検索ボリュームという量的な側面と、ユーザーの検索意図という質的な側面の2つの軸で整理されます。
まず、基本的な分類である検索ボリュームの大小に注目すると、キーワードは以下の3つに大別されます。
| 用語 | 詳細 |
|---|---|
| ビッグキーワード | 「SEO」のように1語で構成され、検索ボリュームが非常に大きい 幅広いユーザーに届くが、競合が激しい |
| ミドルキーワード | 「SEO対策 方法」のように2語程度で構成され、検索ボリュームと競合性のバランスが取れている |
| ロングテールキーワード | 「コンテンツSEO 記事作成 コツ」のように3語以上で構成され、検索意図が具体的で成約率が高い |
ビッグキーワードが1万以上、ミドルキーワードが1,000~1万、ロングテールキーワードが10~1,000というのが検索ボリュームの目安です。
さらに、検索意図の観点からキーワードを分類し、以下の表にまとめました。
| クエリ種別 | 詳細 | 例 |
|---|---|---|
| Knowクエリ | 情報収集を目的とした検索 | 「SEOとは」「SEO対策 やり方」 |
| Goクエリ | 特定サイトやブランドへの訪問を目的とした検索 | 「Amazon ログイン」「Instagram」 |
| Doクエリ | 行動や操作を実行するための検索 | 「アプリ ダウンロード」「航空券 予約」 |
| Buyクエリ | 商品購入やサービス利用を前提とした検索 | 「SEOツール おすすめ」「ノートPC 激安」 |
それぞれの種類を正しく認識し、自社のビジネスモデルに合わせてキーワード選定を行い、成果につなげましょう。
SEOにおけるキーワードの選び方の手順・流れ
SEOにおけるキーワードの選び方の手順・流れは、以下のとおりです。
- ターゲットと目的を明確に設定
- ユーザーの検索意図を理解
- キーワード候補のリストアップ
- 検索ボリュームと競合性の調査
- 優先度の決定
- コンテンツテーマへの落とし込み
- 定期的な見直しと改善
ビジネスの成果に直結するキーワードを見つけるため、7段階の具体的な選定プロセスを一つずつ実践しましょう。
ターゲットと目的を明確に設定
キーワード選定では、「Webサイトで誰に何を伝えたいのか」というターゲットと目的の明確化が最初の作業です。
目的が曖昧なままでは、どのようなキーワードがビジネスの成果につながるのかを正しく判断できないからです。
たとえば、「商品の購入を促したい」「ブランドの認知度を高めたい」では、選ぶべきキーワードの種類は大きく異なります。
Webサイトを訪れるターゲットユーザーを詳細に想定すると、どのような言葉で検索するかを想像しやすくなります。
ユーザーの検索意図を理解
自社の製品・サービス・ブランド・テーマなどに合致するユーザーが、どのような検索意図をもっているか明確化しましょう。
ターゲットユーザーの検索意図を理解するには、背景にある課題や悩みを深く掘り下げる分析が不可欠です。
一例として健康食品を販売する企業の場合、ターゲットユーザーはおいしさ・健康・美容などを求めていると考えられます。
ただし、一から検索意図を分析するのは手間がかかるため、AIの活用や競合他社のWebサイト分析がおすすめです。
具体的には、AIに自社サイトのURLを入力し、想定されるターゲットユーザーの検索意図について出力させましょう。
また、競合サイトをUbersuggestなどのツールで分析すれば、どのような検索意図とキーワード群が必要なのかがわかります。
ターゲットユーザーの抱えている悩みや課題を明確にすれば、キーワード選定において軸をぶらさずにコンテンツの土台を作れます。
キーワード候補のリストアップ
ターゲットと検索意図が明確になったら、軸に沿って考えられるキーワードの候補を幅広くリストアップする工程に移ります。
最初から絞り込みすぎると有望なキーワードを見逃してしまう恐れがあるため、まずは質より量を重視して洗い出しましょう。
自社に関連する主要な単語だけでなく、ユーザーが使いそうな類義語や、より具体的な悩みを示す言葉も候補に含めてください。
ビッグキーワードを選定したら、以下のツールを活用して関連・再検索キーワードを抽出するのが効率的です。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Ubersuggest | サジェスト・関連キーワード・検索ボリューム・SEO難易度・CPC・トレンド分析が可能 |
| ラッコキーワード | 関連キーワードおよび再検索キーワードの一覧取得に対応 |
| GetKeyword | 関連・再検索キーワードを無料で調査できる |
| Googleキーワードプランナー | 関連キーワード・検索ボリューム・競合性が取得可能 |
| Googleトレンド | 検索回数の推移を可視化し、流行や関心度の変化を把握できる |
なお、AIを利用すると自社のサービスに関連するビッグキーワードの選定が、スムーズに進むのでおすすめです。
検索ボリュームと競合性の調査
キーワード候補をリストアップしたあと、先述のツールを活用して検索ボリューム・競合性を調査し、客観的なデータで評価します。
「検索ボリュームがゼロ」「競合が強すぎる」といった事態を避けるため、感覚だけでキーワードを選ぶのは厳禁です。
検索ボリュームが大きいキーワードは大手企業がひしめく激戦区であるケースが多く、新規参入で上位を狙うのは困難です。
ビッグキーワードに挑戦するのは、ドメインオーソリティが少なくとも30近くになってからにしましょう。
ドメインオーソリティとは、Moz社が開発した検索エンジンからの信頼性を示す指標で、1~100のスコアで表されます。
優先度の決定
調査したデータを基にリストアップしたあと、どのキーワードから優先的にコンテンツを作成していくか決めましょう。
すべて同時に取り組むのは非効率なため、ビジネスへの貢献度や上位表示の実現可能性を考慮して順位づけを行います。
自社が提供するサービスからそのキーワードが近いか遠いかが、優先度を決めるための大切な要素です。
検索ボリュームだけで判断するのではなく、自社の商品・サービスの成約につながるかどうかを基準としましょう。
立ち上げ初期は競合が少ないロングテールキーワードから上位表示を狙い、Webサイト全体の評価を高める戦略が有効です。
コンテンツテーマへの落とし込み
一つひとつのキーワードを、実際に作成する記事のテーマ・タイトル・記事構成へと落とし込みましょう。
記事構成を作成する一般的かつ大まかな流れは、以下のとおりです。
- 関連・再検索キーワードを調査して書き出す
- メインキーワードの顕在・潜在ニーズを分析する
- メインキーワードで上位表示されている記事の中見出し(H2タグ)を調査して抽出する
- 中見出しの要不要を判断し、流れを整理して大まかな記事構成を作る
- 中見出しの内容で検索して小見出し(H3タグ)を肉付けしていく
- 関連・再検索キーワードをそれぞれの見出しで回収する
- メインキーワードを可能な限り左側に配置しながらタイトルを作成する
関連・再検索キーワードは実際のユーザーの検索行動を示すため、事前に調査してニーズを確認しましょう。
また、メインキーワードは一つに絞り、検索するユーザーの疑問や課題をすべて解決できるコンテンツを目指してください。
くわえて、文章の量に対する情報の濃度をできる限り高め、一次資料など信頼性のあるソースを基に執筆するのがポイントです。
定期的な見直しと改善
キーワード選定とコンテンツ公開は一度きりの作業ではなく、効果を測定して定期的に見直し、改善を繰り返すのが大切です。
検索エンジンの評価基準や検索トレンドは常に変化しており、公開当初は最適だったコンテンツも時間とともに陳腐化します。
また、公開した記事の検索順位が思うように上がらない場合、コンテンツの質を見直してリライトをするのがおすすめです。
記事のアクセス数や検索順位が上がらないときの課題とリライト方針を、以下の表にまとめました。
| 課題 | 改善ポイント |
|---|---|
| CTRが低い | タイトル・ディスクリプションを見直す |
| 直帰率が高い | 記事冒頭の導入文や構成を改善する |
| 滞在時間が短い | 見出し・本文をわかりやすく整理し、内部リンクを強化する |
| コンバージョンが少ない | CTAの位置や文言を改善する |
| 検索順位が伸びない | コンテンツの一部、もしくはすべてを見直す |
| 情報が古い | 最新データ・統計・事例を追加する |
| 離脱率が高い | ページ速度改善・モバイル最適化を行う |
Googleサーチコンソールなどを活用し、実際の表示順位やクリック率といったデータを分析して改善に役立てましょう。
SEOのキーワード選定における注意点とコツ
SEOのキーワード選定における注意点とコツは、以下のとおりです。
- 検索意図とずれないようにする
- 検索ボリュームだけに依存しない
- 過度なキーワードの詰め込みを避ける
- 難易度の低いロングテールキーワードを活用する
- トレンドの変化を無視しない
- ビジネスゴールとのずれを避ける
失敗を回避して余計な労力やコストをかけないため、注意点を十分に意識してSEOのキーワード選定を行いましょう。
検索意図とずれないようにする
キーワード選定ではユーザーの検索意図を正確に読み取り、提供するコンテンツ内容とずれないように意識しましょう。
ユーザーが求める情報とコンテンツの内容が一致しなければ、たとえ上位に表示されても、訪問者は即座にWebページを離脱します。
もし、検索意図がわかりづらいキーワードがある場合は、生成AIに質問するとおおよそ正しい回答が出力されます。
また、実際にキーワードで検索を行い、上位表示されているコンテンツの内容を確認するのも有効な分析方法です。
検索ボリュームだけに依存しない
キーワード選定において検索ボリュームの数値の大きさだけで判断するのは、危険な落とし穴です。
検索ボリュームが非常に大きいキーワードは、一般的にユーザーの目的が広範で曖昧なケースが多く、上位表示が困難です。
そのため、成約などの成果につながりにくく、労力とコストだけがかかってしまうケースも少なくありません。
ビッグキーワードで圏外にいるよりも、ロングテールキーワードで上位表示されるほうが価値があります。
検索ボリュームという量的なデータと合わせ、ユーザーが自社の顧客になりうるかという質的な関連性を天秤にかけましょう。
過度なキーワードの詰め込みを避ける
上位表示を狙うあまり、コンテンツ内に不自然なほどキーワードを詰め込むキーワードスタッフィングは避けましょう。
キーワードスタッフィングは可読性を損なうだけでなく、Googleのガイドラインに違反するスパム行為と見なされるからです。
2010年代初頭には効果がありましたが、現在の高度に進化した検索エンジンは文脈や関連性を理解しています。
基本的に記事構成さえ十分に作り込めれば、コンテンツ執筆時にキーワードを無理に意識する必要はありません。
コンテンツ執筆時はキーワードの配置より、読者にとって読みやすく役立つ文章にするのが大切です。
難易度の低いロングテールキーワードを活用する
Webサイトの立ち上げ初期や競争の激しい市場では、難易度の低いロングテールキーワードをまずは狙いましょう。
ロングテールキーワードは検索数自体が少ないものの、ユーザーの悩みや要求が非常に具体的で成果につながりやすいのが特徴です。
また、ドメインオーソリティが低い状態でも上位表示が可能で、検索エンジンからの評価を上げる糸口にもなります。
自社の専門分野においてロングテールキーワードを着実に攻略し、成功体験を積み重ねていくのが大切です。
トレンドの変化を無視しない
キーワード選定は一度で完結させず、トレンドや季節といった外部環境の変化を常に捉え、継続的に見直しを行いましょう。
ユーザーの興味や関心は常に変化しており、新しいキーワードが突然注目を集める場合もあるからです。
具体例を挙げると、「新しいスマホの機種名」「冬のお歳暮関連」「SNSでバズった単語」などです。
Googleトレンドを活用し、自社がターゲットとする市場のキーワードの変動を定期的に観測しましょう。
ビジネスゴールとのずれを避ける
選定したキーワードが自社のビジネスゴールとずれていないか、分析や確認をするのが重要です。
多くのアクセスを集めるキーワードで上位表示できても、流入が事業上の成果に結びつかなければ意味がありません。
一例を挙げると、Web制作会社のオウンドメディアで、生成AIの解説記事を掲載しても成果につなげるのは困難です。
集客という手段が目的化しないよう、常に最終的な事業目標から逆算してキーワードを考えるようにしましょう。
無料もあり!SEOのキーワード選定に役立つ調査・チェック・分析ツール
SEOのキーワード選定に役立つ調査・チェック・分析ツールは、以下のとおりです。
- Googleキーワードプランナー
- ラッコキーワード
- Ubersuggest
- Semrush
目的に合ったツールを活用し、データに基づいた客観的なキーワード選定でビジネスの成果を手に入れましょう。
Googleキーワードプランナー
Googleキーワードプランナーは、キーワードの月間検索ボリュームや関連キーワードを調査できるツールです。
Googleの検索データを基にしているため、表示される情報の信頼性が非常に高いのが大きな特徴です。
「新しいキーワードを見つける」機能では、サービス名などを入力するだけで、関連性の高い新たなキーワード候補を発見できます。
本来はGoogle広告への出稿を検討している人向けのツールですが、SEOのキーワード選定でも広く活用されています。
広告を出稿するとさらに詳しい検索ボリュームがわかりますが、無料でも大まかな分析には十分に役立つのでおすすめです。
ラッコキーワード
出典:ラッコキーワード
ラッコキーワードは、無料で関連・再検索キーワードを網羅的に取得できる便利なツールです。
Google以外の検索エンジンのキーワードも取得できるため、ユーザーの多様な検索ニーズを短時間で把握できます。
また、「潜在的な検索キーワード/質問」機能を使えば、「ツリー」タブで再検索キーワードの取得も可能です。
さらに、「見出し抽出」機能なども備わっており、記事構成に欠かせないツールとして多くのユーザーが利用しています。
会員登録をしなくても基本的な機能は無料で利用できますので、まずは関連キーワードなどの調査に活用してみましょう。
| プラン | 月額料金 |
|---|---|
| フリー | 無料 |
| ライト | 990円~ |
| スタンダード | 2,475円~ |
| プロ | 4,950円~ |
| エンタープライズ | 9,900円~ |
※税込表示
Ubersuggest
出典:Ubersuggest
Ubersuggest(ウーバーサジェスト)はキーワード調査だけでなく、Webサイトの分析やSEOの状況チェックも可能な多機能ツールです。
キーワード選定・競合リサーチ・Webサイトの技術的な問題点の発見までを一つのツールで広くカバーできます。
特に競合分析機能を使えば、ライバルサイトがどのようなキーワードでアクセスを集めているかを分析できるのが魅力です。
世界的なマーケターであるニール・パテル氏によって開発されており、わかりやすく整理された管理画面も人気の理由の一つです。
無料でも一部の機能は利用できますが、すべてのツールを使えるようにするには月額課金か買い切りでの購入が求められます。
| プラン | 月額料金 | 買い切り |
|---|---|---|
| パーソナル | 2,999円 | 2万9,990円 |
| ビジネス | 4,999円 | 4万9,990円 |
| エンタープライズ | 9,999円 | 9万9,990円 |
※税込表示
Semrush
出典:Semrush
Semrush(セムラッシュ)は世界中のマーケターに利用されている、SEO対策を含む包括的なデジタルマーケティング支援ツールです。
競合サイトの分析機能が非常に強力で、評価されているキーワード以外にも広告出稿の状況や被リンクまで詳細に把握できます。
また、URLを入力するだけで現在のSEOにおける立ち位置や強化すべき改善点を多角的に分析し、レポートとして可視化します。
キーワード調査からテクニカルSEOまで機能が豊富なため、本格的に施策に取り組む中級者から上級者向けのツールです。
| プラン | 月額料金 |
|---|---|
| Proプラン | 153.95ドル |
| Guruプラン | 274.95ドル |
| Businessプラン | 549.95ドル |
※税込表示
ホームページやブログ記事へのSEOキーワードの入れ方・やり方
ホームページやブログ記事へのSEOキーワードの入れ方・やり方は、以下のとおりです。
- タイトルへ挿入
- 見出しで回収
- 本文中・ディスクリプション・画像で自然に配置する書き方
- 内部リンクのアンカーテキストに使用
それぞれのやり方をあらかじめ頭に入れておき、コツを掴んでスムーズにコンテンツを制作しましょう。
タイトルへ挿入
記事のタイトルには、必ず選定したメインキーワードをできる限り前半部分に配置するのが大切です。
タイトルは検索結果ページでユーザーの目に最初に触れる要素であり、クリック率を直接的に左右するからです。
検索エンジンはタイトルに含まれる語句を、ページ内容を判断するための最重要シグナルとして扱います。
そのため、メインキーワードだけでなく関連・再検索キーワードも可能な限りタイトルに含めましょう。
なお、タイトルの文字数についてはさまざまな考え方がありますが、30文字~40文字までというのが一般的です。
見出しで回収
Webページのタイトルに次いでキーワードを配置すべき重要な場所が、文章全体の骨格を形成するH2やH3などの見出しです。
コンテンツ内の見出しが果たす2つの役割は、以下のとおりです。
- 検索エンジンにコンテンツのテーマと階層構造を論理的に伝える
- ユーザーが文章の要点を素早く把握できる
なお、見出しで回収するときは関連・再検索キーワードの全文を入れる必要はなく、共通しないフレーズを含めるのがコツです。
一例を挙げると、「SEO キーワード」の関連キーワードの一部は以下のとおりです。
- SEO キーワード出現率
- SEO キーワード選定 ツール
- SEO キーワード チェック
上記の関連キーワードを見出しで回収するときに、「出現率」「選定ツール」「チェック」などを含めるのがポイントとなります。
中見出し(H2)にメインキーワードを盛り込み、小見出し(H3)で関連・再検索キーワードを回収しましょう。
本文中・ディスクリプション・画像で自然に配置する書き方
タイトルや見出しだけでなく、本文・ディスクリプション・画像でもキーワードを自然な形で配置しましょう。
ただし、記事構成をキーワードと検索意図に沿って作り込めば、本文では自然にキーワードが入るものです。
そのため、あくまでユーザーにとって読みやすく、理解の助けとなる形でキーワードを使用するのが評価につながります。
無理に入れるのではなく、丁寧に解説した結果、キーワードや関連語が自然と文章に含まれている状態を目指しましょう。
内部リンクのアンカーテキストに使用
内部リンクを設置するとき、テキストにキーワードを使用するのは効果的なSEO施策の一つです。
アンカーテキストは、ユーザーだけでなく検索エンジンに対しても、リンク先のページの内容を伝えるシグナルとして機能します。
たとえば、「詳細はこちら」ではなく、「SEOキーワードの選定方法」のような具体的なアンカーテキストにしましょう。
関連性が高い記事同士を具体的なアンカーテキストで結びつけ、Webサイト全体の評価を着実に積み上げてください。
SEOのキーワードや選定方法に関するよくある質問
SEOのキーワードや選定方法に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- キーワード選定は難しいですか?
- SEO対策におけるキーワードの数・順番・比率などについて教えて
- 関連キーワードが多すぎる場合に記事制作はどうすればよい?
初心者が抱く疑問をあらかじめ解消し、効果的なキーワード選定への第一歩を着実に踏み出しましょう。
キーワード選定は難しいですか?
キーワード選定は正しい手順とコツを知らないと難しく感じますが、基本を押さえれば初心者でも実践できます。
多くの人が難しさを感じるのは、専用ツールの使い方やユーザーの検索意図の分析など、慣れない作業が含まれるためです。
まずは自社の顧客がどのような言葉で検索するかを想像し、関連キーワードを洗い出す作業から始めるのがおすすめです。
SEO対策におけるキーワードの数・順番・比率などについて教えて
キーワードの数や比率を機械的に調整するより、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成するのがSEOでは重要です。
かつてはキーワードの出現率が重視された時代もありましたが、現在の検索エンジンでは不自然な詰め込みは逆効果となります。
クオリティの高い記事構成さえ作れば、執筆段階で自然とメイン・関連・再検索キーワードが文章に盛り込まれます。
数・順番・比率などを気にせず、ユーザーの検索意図を十分に分析し、課題を解決できる良質なコンテンツを目指しましょう。
関連キーワードが多すぎる場合に記事制作はどうすればよい?
関連キーワードの候補が多すぎる場合は検索意図ごとに分類し、複数の記事に分けてコンテンツを作成する方法が効果的です。
一つの記事に関連キーワードを無理に詰め込むと、専門性が薄まり、どのユーザーの悩みにも応えられないコンテンツになります。
まとめ
SEO対策におけるキーワードは、タイトルや本文へ適切に盛り込んで検索エンジンにコンテンツの内容を伝える役割があります。
効果的なキーワード選定を行うには、まずターゲットと目的を定めてユーザーの検索意図への深い理解が必要です。
Webサイトの初期段階では、競合が少なく成約率が高いロングテールキーワードで上位表示を狙う戦略が有効です。
キーワードはユーザーの検索意図からずれないよう注意し、タイトルや見出しへ自然な形で配置してください。
データに基づいた客観的なキーワード選定を実践し、SEO対策を成功させて自社のビジネスを加速しましょう。
また、当サイト「ビズサイ」ではサブスク型ホームページ制作サービスを提供しています。
低コストながらのオリジナルデザインで、SEOの内部対策を施したホームページを制作します。
ホームページの公開後は保守管理やセキュリティ対策などのサポートをしており、月額費用は5,478円(税込)からです。
新規開設やリニューアルでお困りの方は、ビズサイにお任せください(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。
まずは無料でご相談ください。
お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。
※年末年始・土日祝は定休日となります
※受付時間 9:00~17:30